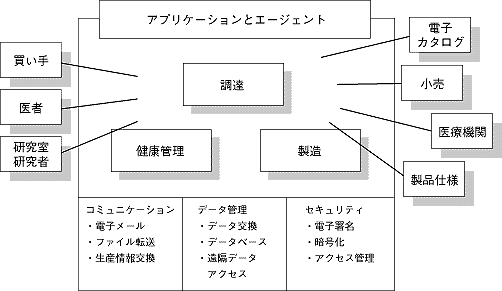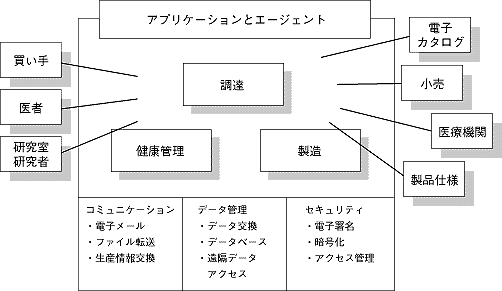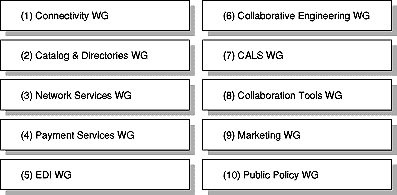【前へ】
2.2.5 コマースネットの研究成果詳細
これらの実験プロジェクトの中でも、最もアクティビテイの高いコマースネットに着目し、その内容と体制を整理する。
コマースネットは、一地域における実証プロジェクトに過ぎないが、エレクトロニック・コマースに関連する代表的な企業が数多く参加しており、外部のエレクトロニック・コマース実験にも影響を及ぼすほどの先進性、規模を持っている。従って、今後のエレクトロニック・コマースにおけるデファクト・スタンダード的な意味を持つと考えられる。
2.2.5.1 コマースネットの概要
コマースネットは、インターネット上でエレクトロニック・コマース(電子商取引)を実現するための大規模な実証実験を行なう非営利コンソーシアムである。
コマースネットの設立は、1993年TRP(Technology Reinvestment Project)に対して提案されたEIT(Enterprise
Integration Technologies)、BARRNet(Bay Area Regional Research Network)、スタンフォード大学のCIT(Center
for Integration Technologies)の三者によるものが発端である。この提案は、カリフォルニア州政府及びスマートバレー公社の強い支援を受けていたことから、1994年4月から3年間のプロジェクトとして連邦政府から認定され、600万ドルの予算を獲得した。また、コマースネット参加企業から、同額(600万ドル)のマッチング・ギフトを受けている。
設立当初のコマースネットのメンバーは、シリンコンバレー地区の半導体、コンピュータ及び金融機関を中心に、その顧客、取引先、関連する公的機関で構成されていた。
このようにコマースネットそのものは、カリフォルニア州北部を中心に開始されたプロジェクトであるが、現在では州外からの参加も可能であり、他地域のエレクトロニック・コマース実験プロジェクトとの積極的な連携も進められている。
2.2.5.2 コマースネットの目的
コマースネットでは、最終的な到達目標として、企業が自由にビジネス情報をやりとりするための使いやすい、オープンな基盤整備を行ない、電子市場を創造することを掲げている。コマースネットでは、今後5年以内に米国内のほとんどの企業・団体がインターネットを通じてビジネスを行なうであろうと想定している。
しかし、現実にはさまざまな課題が存在しており、その課題克服のためにコマースネットでは電子市場確立のための大規模市場実験を行ない、次のような成果を想定している。
- 解決すべき課題の明確化
- 明確化された課題を踏まえて、エレクトロニック・コマースに必要とされる技術、アプリケーション、ビジネスプロセスの標準化の推進
2.2.5.3 エレクトロニック・コマースによる企業、一般消費者への効果
エレクトロニック・コマースの普及により、次のような効果が考えられる。
(1)調達、購買業務の合理化
- 電子化により、注文、支払い等の各プロセス間の時間の遅れがなくなるとともに、伝票等の扱いによる間違いもなくなる。この結果として、調達・購買業務が正確かつ迅速なものとなる。
(2)製品のライフサイクル(研究開発〜生産〜生産停止)全体のコスト低減
- 製品の開発段階から、オープンにすることで広範囲な競争入札が行なわれ、開発コストが低減できる。さらに、製品の生産・販売段階では、電子カタログによる広告宣伝費及び営業経費の低減、電子決済による手数料の低減等が挙げられる。また、ソフトウェアや書籍などのように電子的に配送できるものについては、在庫コスト及び流通コストが削減できる。
(3)製品開発期間の短縮
- 設計者、製造担当者、関連業者などがネットワーク上で情報を共有するともに、親密な双方向のコミュニケーションをとることが可能となり、製品開発期間の短縮が期待できる。
(4)仮想企業の出現
- ネットワークにより遠隔地の企業であっても、距離を意識することなくコミュニケーションが可能となり、企業の枠を越えた目的指向のプロジェクトチームが形成される。プロジェクトごとに適任者で構成され、従来の企業のように自社内に資源を抱え込む形での経営は、環境変化への俊敏な対応ができなくなると想定される。
(5)中小企業のビジネス機会の獲得
- ネットワーク上で事業展開を行なうことにより、これまでの大企業が保有していたチャネルや人的ネットワークを中小企業でも獲得することが可能となってくる。そこでは、広告宣伝費を掛けなくても電子カタログのデザインさえできれば、費用を掛けることなく市場開拓が可能となる。
(6)新たな情報サービスの出現
- ネットワーク取引が活発に行なわれることにより、これまで存在し得なかった新種のサービスが生まれてくる。例えば、膨大な電子カタログの中から希望する商品を検索する統合ディレクトリ・サービス、入札者と応札者との引き合わせを行なうブローカーサービス、ネットワーク上での決済を行なうための電子決済サービス等が新たなサービスとして考えられる。
電子データによる商取引はこれまでも行なわれてきたが、その形態は事前に取り決めを行なった特定の企業間または個人間に限られており、商用
VAN などの専用線ネットワークを用いたものであった。この形態では、規模の大きな企業でなければメリットを享受することが難しく、限定顧客対象であるという大きな課題が存在してきた。
コマースネットでは、こうした課題を解決するためにグローバルな顧客獲得と事業協力者を確保するために、エレクトロニック・コマースの媒体としてインターネットを選んでいる。インターネットを使った必要最低限の電子データのやりとりは、ワークステーション1台と電話回線を用意すれば十分であり、中小企業や個人にとって大きな負担を強いるものではない。また、インターネットに関する技術を保有しない企業に対しては、コマースネットが有償で技術的支援を行なっている。
ただし、インターネットを利用した場合には、次のような課題が発生する。
(1)アクセスが難しいこと
- これまでインターネットは技術者向けのネットワークとして発展してきたため、一般ビジネス分野での応用は始まったばかりである。そのため、技術者不足等の原因によりアクセスが一般的に難しいとされている。
(2)情報検索機能が弱いこと
- インターネット上の情報資源は、各サイトが独自に管理するため、それらの情報を一元的に管理、統合する仕組みはない。そのため、どこに自分の知りたい情報があるかを探すことが難しい。
(3)セキュリティが甘いこと
- インターネットは、データが不特定多数のさまざまなサイトを経由して運ばれるため、あるサイトを通過する情報を観察することで、内容を盗み読んだり、改ざんすることは可能である。そのため、クレジットカード番号やパスワード等のセキュリティ情報が盗まれることは、当たり前に起こると考えておかなければならない。
(4)決済制度がないこと
- セキュリティが甘いことから、金銭の授受においては暗号化などの別手段が必要となる。そのため決済制度が確立していない。
コマースネットでは、これらの課題を克服するために、解決策を検討するとともに、実証実験(パイロット・プロジェクト)によって解決策の妥当性を検証し、エレクトロニック・コマースのための必要な技術及びビジネスプロセスの標準化を進めることを目的としている。
2.2.5.4 コマースネットでの実験項目
コマースネットでは、インターネットのもつエレクトロニック・コマースの媒体として活用する際の課題を克服するために次のようなサービスの提供を計画している。
(1)インターネットのアクセスの難しさの克服
- a. ISDN 接続の安価な提供
- サンフランシスコ湾沿岸を対象として、中小規模の企業・団体が利用可能な
ISDN 接続を安価に提供するサービスを行なう。このサービスは、BARRNetとPacific
Bellの協力のもとで行なわれる。
- b. スターターキットの提供
- インターネット技術の蓄積が少ない企業のためにスターターキットをオンラインで提供している。このキットには、WWWサーバ用ソフト、統計解析ソフト、http変換プログラム等のPDS、シェアウェアが含まれている。
(2)検索機能の貧弱さの克服
- a. マルチメディアカタログの提供
- WWWを標準として採用したハイパーメディアによる洗練されたカタログを提供する。
- b. 高機能なディレクトリサービスの開発
- ユーザが入手したいと思う情報にできるだけ早く到達するために、ハイパーリンクによるディレクトリ情報を提供する。さらに、将来的にはエージェント技術等による高機能な検索機能を開発、提供する。このサービスはCITが研究、開発を担当している。
(3)セキュリティの甘さの克服
- a. セキュリティ確保方式の開発
- 実際のビジネス環境での利用に耐えられるセキュリティの確保のために、公開キー暗号化方式によるユーザ認証、アクセス制御、データ交換セキュリティの研究を行なっている。このサービスはRSA、NCSAとの共同の下にEITが担当している。
- b. セキュリティ実現への障壁回避
- セキュリティ実現に際しての最も大きな障壁は、連邦政府による暗号化ソフトウェアの輸出制限である。コマースネットは連邦政府に対し、輸出規制の緩和とEES(Escrow
Encryption Standard)を再検討するよう要請するレポートを発表した。
(4)決済制度の欠落の克服
- a. カード、電子小切手のパイロットプロジェクト計画
- コマースネットが目指すゴールの一つとして、コマースネットを構成するメンバーの金融機関を通した電子決済機構の実現がある。そのための取り組みとして、クレジットカード、デビットカード、電子小切手に関するパイロットプロジェクトが計画されている。
2.2.5.5 コマースネットの組織
・参加企業・団体
- コマースネットでの実験に参加しいる企業・団体は、次の5つの区分に分類される。
-
- 設立メンバー(Founding Member)
- 出資メンバー(Sponsoring Member)
- 参加メンバー(Associate Member)
- 賛助会員(Subscriber)
- ユーザ(User)
(1)設立メンバー
- 設立メンバーは、コマースネット設立当初からの参加企業・団体で、代表者が理事会(Corporate
Board of Directors)に参加している。
(2)出資メンバー
- 出資メンバーは、コンソーシアムの管理、パイロットプロジェクトへの参加が可能な団体であり以下のような権限を持つ。現在、米国内に本社を持たない企業は出資メンバーとして参加することができない。
-
- 運営委員会(Sponsoring Steering Committee)およびワーキンググループにおける投票権
- メンバーディレクトリへの登録、自社サーバへのコマースネットからのリンク
- プロジェクト成果情報の優先的入手
- プロバイダースターターキットの無償入手
- 「ストア・フロント」セットアップのための技術支援
- トレーニングコースへの無料参加
- コマースネットが関与する会議、展示会等への参加
-
- 出資メンバーとして参加するためには、年間35,000ドルの費用が必要である。
(3)参加メンバー
- 参加メンバーは、出資メンバーとほとんど同じであるが、中小企業をターゲットとした設定になっており、出資メンバーと比較してやや制限されている。
-
- ワーキンググループへの参加権
- メンバーディレクトリへの登録、自社サーバへのコマースネットからのリンク
- プロバイダースターターキットの無償入手
- トレーニングコースへの無料参加
- コマースネットが関与する会議、展示会等への参加
-
- 参加メンバーとして参加するためには、年間5,000〜10,000ドルの費用が必要である。
(4)賛助会員
- 賛助会員は、コンソーシアムのメンバーではない比較的小規模な、コンソーシアムへの参加を希望しない企業等を対象としたものである。
-
- メンバーディレクトリへの登録、自社サーバへのコマースネットからのリンク
- プロバイダースターターキットの無償入手
- トレーニングコースへの無料参加
- 賛助会員メーリングリストへの参加
-
- 賛助会員として参加するためには、年間1,250ドルの費用が必要である。
(5)ユーザ
- インターネットユーザであればだれでも、コンソーシアムメンバーが提供するストア・フロントの顧客として、コマースネットの実験に参加することができる。
2.2.5.6 コマースネットの運営形態
コマースネットは、次のような組織形態に役割分担しつつ、コマースネットを運営している。
開発中心チーム(Core Development Team)
理事会(Corporate Board of Directors)
運営委員会(Sponsoring Steering Committee)
ワーキンググループ
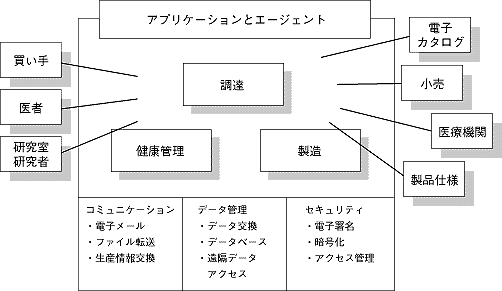
図III−4 参加団体と運営組織の関連
(1)開発中心チーム(Core Development Team)
- 設立メンバーのうち、TRPへの提案に関与したBARRNet、EIT、およびCITの3機関を特に「開発中心チーム(Core
Development Team)」と称している。これらの機関はそれぞれコマースネットの運営上の各側面で重要な役割をになっている。
-
- BARRNetは、Pacific Bellとの協調により、中小規模企業に安価なISDN接続の提供を実現する役割をになっている。
-
- EITは、プログラム全体の管理(WWWサーバの運営を含む)と、ネットワークサービス実現のための技術開発の役割を担っている。特にインターネット上でのセキュリティ保持に関する技術分野に重点が置かれ、Secure
HTTPの開発者であると同時に、NSCA、RSAとの協力により、Secure NCSA Mosaic、Secure
NCSA httpdの開発も行なっている。
-
- CITは、NIIプロジェクトにおける先端技術開発の支援を行なっているが、コマースネットにおいても同様の役割を担っている。特に、エージェント技術をベースにした知的情報検索システムの開発を行なっている。
(2)理事会(Corporate Board of Directors)
- 理事会では、各設立メンバー、カリフォルニア州政府、スマートバレー公社の代表者、運営委員会の議長、および理事長(Executive
Director)をメンバーとしており、コンソーシアムの経理、法務、及び日常活動の管理責任を負う。
(3)運営委員会(Sponsor Steering Committee)
- 運営委員会では、各出資メンバーからの代表、及び参加メンバーの代表者から構成される。運営委員会は理事会と協力し、各メンバーの管理を行なうとともに、ワーキンググループ運営の管理責任を負う。
(4)ワーキンググループ
- ワーキンググループは、エレクトロニック・コマースに関する技術的課題の検討やパイロットプロジェクトの選定等を行なう、コンソーシアムメンバーの集合体である。
2.2.5.7 ワーキンググループの構成
コマースネットでは、サービス実現のための技術面、制度面での具体的な検討を行なうことを目的として、以下の10ワーキンググループを設置、活動している。
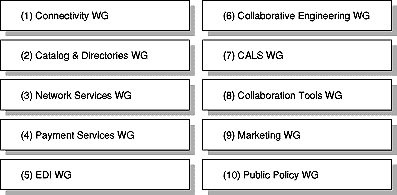
図III−5 ワーキンググループの構成
2.2.6 エレクトロニック・コマースの到達目標
エレクトロニック・コマースプロジェクトのうち、到達目標等が明らかになっているものは、次のようなものが挙げられる。
NIST「エレクトロニック・コマース実験」
<1994年度>
エレクトロニック・コマースを支援するツール類の構造開発
必要とされるセキュリティ・サービスの評価
製造業支援アプリケーションのプロトタイプ開発
デモンストレーション環境の設置
ワークショップの開催と報告書刊行
<1995年度>
電子購入のパイロットシステムのデモンストレーション
セキュリティに関するフレームワークと関連基本サービスの開発
2.2.7 今後の見通し
既に、各種エレクトロニック・コマース実証実験は進められており、電子決済やセキュリティ等も解決手段がいくつか確立しつつある状況にあるといえる。
コマースネットにおける先行的な実証実験も、積極的に展開されていることから、エレクトロニック・コマースの一般への普及は、比較的早いものと予想される。
現段階での技術的ブレークスルーは、
認証機構(セキュリティ機能)
程度であって、これはほぼ克服の目途はついているものと考えられる。さらに、社会的要因として、
決済制度の確立
があるが、これについても、デジキャッシュ等の統一化・標準化により克服されることは確実であろう。
その意味では、産業界全体のニーズとしても、エレクトロニック・コマースに関するニーズは大きなものがあるため、積極的な展開が今後もなされるものと予想され、一般への普及も数年後には確立するものと考えられる。
【次へ】