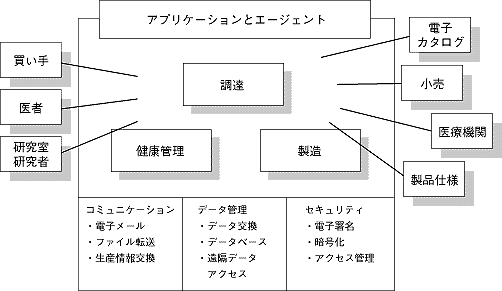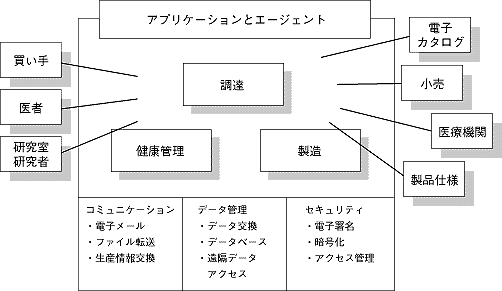【前へ】
2.HPCCにおけるNational Challengesの概況(注3)
HPCC(High Performance Computing and Communications)基金におけるGrand
ChallengesとNational Challengesはそれぞれ大規模な研究開発プロジェクトである。Grand
Challengesにおいては、基礎的な要素技術研究が主体であり、National Challengesでは、実用面を重視した製品、サービスなどの応用技術研究が主体であり、社会的ニーズへの対応が加味されている。
| (注3) |
この章に関しては、National Science and Technology Council,
Committee on Information and Communications のレポート''High Performance
Computing and Communications (Foundation for America's Information Future
)''1996 を基本としてまとめた。詳細については、http://www.hpcc.gov/を参照のこと。 |
1996年予算ベースでの具体的な研究テーマは、次のとおりである。
- Grand / National Challenge Applications
- Grand Challenges
- Applied Fluid Dynamics
- Meso- to Macro-Scale Environmental Modeling
- Ecosystem Simulations
- Biomedical Imaging and Biomechanics
- Moleculer Design and Process Optimization
- Cognition
- Fundamental Computational Sciences
- Grand-Challenge-Scale Applications
- National Challenges
- Digital Libraries
- Public Access to Government Information
- Electronic Commerce
- Civil Infrastructure
- Education and Lifelong Learning
- Energy Management
- Environment Monitoring
- Health Care
- Manufacturing Processes and Products
これらの中から、比較的プロジェクトの成果が表れつつあるNational Challengesの3プロジェクト(デジタル・ライブラリ、エレクトロニック・コマース、製造プロセス及び製品)について、その内容、実施形態、研究開発状況、今後の課題などをまとめ、さらに4プロジェクト(エネルギー・マネジメント、政府情報の一般公開、環境モニタリング、教育と生涯学習)について、概要などをまとめた。
2.1 デジタル・ライブラリ
ライブラリ情報の広範な活用のためには、情報そのものと容易なアクセス手段が必要となる。数年来、電子的に利用可能な情報量が膨大に増えてきており、この電子的情報量の増加状況には、HPCCから出資、あるいはHPCCの関連団体が牽引的役割を果たしたプロジェクトによる成果がいくつか見られる。それらは、
- インターネットとその拡大
- クライアント/サーバ技術(ワークステーションからのサーバへの遠隔接続)
- WWW技術(URL、HTML、HTTPなど)によるインターネットを経由した認証技術と情報へのアクセス技術
- 操作性の簡単なかつ拡張性の高いWWWへのアクセスのできるNCSA Mosaic
である。
以下、2.1.1〜2.1.7まで、デジタル・ライブラリに含まれるプロジェクトを示す。
2.1.1 デジタル・ライブラリ共同研究
1994年、NSF、ARPA、NASAは共同でデジタル・ライブラリ研究および技術開発に対して4年単位の出資を行なった。その対象である6つの研究グループは、それぞれリーダーとなる大学と10以上の団体(図書館、博物館、出版社、学校、コンピュータベンダー、通信事業者など)によって構成されている。
この共同研究の目的は、デジタル化された情報の収集、蓄積、統合と検索、加工をユーザーフレンドリーな方法で通信ネットワークを介して可能にすることである。このプロジェクト群は、人間とコンピュータのインタラクション、収集管理と保存方法、図書司書の考え方、利用者の評価などの点も関連テーマとしてとらえている。さらに、これらのプロジェクト群は教育要素への展開も含んでいる。
以下、6つのプロジェクト(注4)を示す。
| (注4) |
この6つのプロジェクトに関しては、個別にWWWサーバ上で研究状況が示されている。 |
(1)環境ライブラリ
(拡張性のある知的分散型ライブラリのプロトタイプ)
- これは、カリフォルニア大バークレー校がリーダーとなっているもので、カリフォルニア州の環境をテーマとしたデジタル・ライブラリのプロトタイプを作成することを目的としている。そこでの情報は、環境に関連する条例や報告書類だけではなく、写真、ビデオ、コンピュータ上のモデル、州の基本計画、地図、さらには環境情報に関するデータベースまでを含んだものが考えられている。これらのマルチメディア情報を、データベースを中心としたクライアントサーバシステムを活用して、環境に関する計画・研究を州レベルやそれ以下の地域レベルで利用することを可能にするものである。この研究開発は、自動インデックス付与や知的検索プロセス、データベース技術、データ圧縮や通信ツールなども研究対象として含んでいる。
(2)ミシガン大学デジタル・ライブラリ・プロジェクト
- このプロジェクトは、地球および宇宙に関する科学データの巨大なマルチメディア環境を創造することを目的としている。そこでは、ページ単位のイメージから双方向かつ柔軟性のあるドキュメントまで、さらには利用者の指示ごとにリアルタイムでの科学データを含んだインタラクションを可能にすることを目指している。それは、人類がこれまで体験してきた実験を再現する形にもなる。
- この研究では、ユーザインターフェース、仲介機能、インターフェースエージェントの集合体といったソフトウェアエージェントの構築を目標としている。さらには、多数のユーザと情報リポジトリを接続することで、インターネット上の莫大な量の情報を論理的に扱うことのできるシステム構築が目指されている。
(3)アレキサンドリア・プロジェクト
- このプロジェクトは、カリフォルニア大学サンタバーバラ校で行なわれているもので、巨大かつ深度の深い地図、画像さらには将来のデジタル・ライブラリで行なわれるであろうサービスを包含する画像情報に対して、容易なアクセスを可能にすることに目的を置いている。
- 当面の目的は、大きな地図製作法の蓄積(現在では、総アイテム数400万アイテム)を電子的にアクセス可能な形態にし、情報の所在マップと地理的に分散しているデジタル・ライブラリとデータベースをなんらかの統合インデックスで結ぶことである。そのテスト環境は、ユーザインターフェース、カタログ、収納方法および各構成要素に分割されている。コンテンツを中心とした検索は、カタログ要素に対して開発される予定である。
(4)スタンフォード・知的デジタル・ライブラリ・プロジェクト
- スタンフォード大学での知的デジタル・ライブラリ・プロジェクトは、多数のネットワークで接続された資源および蓄積へのアクセスを一つの巨大な「仮想」ライブラリとして扱うことを可能にする統合技術を開発することを目的としている。ここで対象としている情報資源は、個人の情報蓄積から現在の一般的なライブラリや科学者が共有している巨大なデータ蓄積までを範囲としている。
- ここでの主たる成果物は、どのようなバックグラウンドをもつユーザでも、世界的な蓄積資源を標準化された操作で扱うことのできる技術(ここでは「グルー」と呼ばれている)を構築することである。
(5)イリノイ大学
- イリノイ大でのプロジェクトは、NCSAのMosaicをカスタマイズすることを目的としている。プロトタイプは、情報資源に対して緊密な接続と適したフォームでの表示を行なう「インタースペース」を形成することによって、インターネットブラウザを用いてライブラリの情報にアクセスすることを可能にするものである。
-
- 当面は、工学および科学分野の刊行物、雑誌などの蓄積に重点を置いている。そこでは、全文を対象とし、テキスト、画像、表、脚注、参照などすべてを含んでいる。
(6)インフォメディア・プロジェクト
- このプロジェクトはカーネギー・メロン大学がリーダーとなっているもので、双方向のデジタルビデオのライブラリシステムを開発することを目的としている。このシステムは、演説、映像、技術を説明する自然言語などで構成されるライブラリで、音声およびビデオ素材のコンテンツベースでの検索を可能にする。このライブラリの環境は、当面、1000時間の民間放送と教育映像ライブラリのビデオから構成される。この段階でのユーザは、小学校、中学校の学童・生徒が想定されている。
2.1.2 デジタル・ライブラリ技術プロジェクト(注5)
NASAはデジタル・ライブラリ技術の研究開発にリモート・センシング画像のアクセス支援および集配信、特に公共・民間の両方に使える拡張性の高いアプリケーション、に対して出資を行なっている。共同研究の早期成果を期待して1994年度および1995年度初頭に7つのデジタル・ライブラリ技術プロジェクトに出資を行なった。その対象は、公立学校、博物館、大学、一般民間企業が含まれている。
| (注5) |
詳細については、
http://sdcd.gsfc.nasa.gov/ISTO/DLT/dit_projects.htmlを参照のこと。 |
これら7つのプロジェクトは次のようなものである。
(1)統合空間データアクセス研究組合
- これは、ベル通信研究所が行なっているもので、NASAの画像やその他の地球空間データを扱うツール開発を目的としている。そこでは、位置情報、アクセス、ブラウジング、転送、再利用ができる形をとる。ツールは、GUI、デザイン、データスクリーニング、データ圧縮、分散データベース技術などの新しいソフトと既存のパブリックドメインのソフトウェアを統合させる形をとる。
(2)デジタル映像のコンテンツ検索システム研究
- このプロジェクトは、IBMが担当しているもので、コンテンツをベースとした検索を画像の引用アルゴリズムを改良し、スピードアップを図ることを目的とする。現在のシステムでは、検索可能な方法に制限があり、また、効果的な検索を行なうためのデータベースの大きさにも制限がある。ここでのテスト環境は、100GB以上の情報を扱う技術が用いられている。
(3)家庭からのNASAへのアクセス
- このプロジェクトは、コンピュータサイエンス社が実施しているもので、CATV網を使ったインターネットへのアクセスを行なうものである。具体的に、CATVから主婦がインターネットにアクセスすることが可能になるようないくつかの基盤をフィールド実験するものである。
(4)公的接続の検証:リアルタイムの地球・宇宙科学データの双方向実験
- このプロジェクトは、ライス大学が、年間200万人が訪れるヒューストン自然科学博物館と連携した形で進められている。そこではインターネットを中心に置くことによって、NASAのリアルタイムに近いデータ、映像等をライス大学から博物館に転送し、プラネタリウムのプログラムの形で一般の人々がコンピュータによる双方向情報窓口や宇宙、地球科学の問題解決型シミュレーションを行なうことを目的としている。
(5)プロジェクト・ホライズン
- このプロジェクトは、イリノイ大学が行なっているもので、インターネットを通して、地球と宇宙の科学データの両方を移動、統合、分析するデジタル・ライブラリ技術を一般に提供することを目的とするものである。数多くの共通フォーマットのデータを統合させた科学データサーバの開発を含めて、Mosaicのようなソフトウェアや拡張性を持ったサーバ、情報システムの研究開発を行なっている。
(6)デジタル映像の圧縮、転送
- このプロジェクトは、ウィスコンシン大学が行なっているもので、新しい圧縮技術とサーバを用いた転送プロトコル、視覚化ソフトウェアの提供を行なうことを目的としている。ここでのプロトタイプは、100程度の要素を含んだ定義が可能な形態になっている。
(7)SAIRE−エージェントベースの情報検索エンジン
- これは、ローラル・エアロシステム社が実施しているもので、インターネットを通して、合衆国グローバル・チェンジ・マスター・ディレクトリから地球および宇宙に関する科学データを利用する熟練者と初心者の両方に適用可能なソフトウェアを開発することを目的としている。知的ソフトウェアエージェントを用いることで、このソフトウェアは自然言語フォーマットや構造化されたクエリーやメニューによって、指示を簡単な表現で実行することを目指している。さらに、間違い訂正や欠落した情報の補完やユーザガイドなどによって、込み入ったクエリーメカニズムからユーザを守る仕組みになっている。
NASAは、1995年度の後半から第2段階のデジタル・ライブラリ技術のパートナー選びを進めている。この選定作業は、1996年になされる予定である。
2.1.3 衛星気象データ転送(注6)
気象衛星NOAAのデータ蓄積は赤道上の環境データ測定用の気象衛星NOAAからのリアルタイムや時系列データのデジタル・ライブラリである。2TBのライブラリは、50TBを扱えるよう拡張されたIBMのロボティックテープ装置に搭載されている。
| (注6) |
詳細については、http://www.saa.noaa.gov/を参照のこと。 |
利用者は、衛星画像の一覧を検索でき、地球の画像をプレビューしたり、さらなる加工や分析のためにダウンロードすることができる。アプリケーションとしては、気象分析、気象予報、気候研究および予測、海洋表面温度測定、気温・湿度の環境予測、海洋動態研究、火山活動モニタリング、森林火災予防などが含まれている。
2.1.4 環境意思決定
1996年度からEPAでは、自然発生的な環境データの分散資源を用いた知的双方向総合分析技術の開発に対して、調査を予定している。この調査では、データ蓄積、インデックス付与、クエリー生成、フィルター・合計加工などを目標としており、情報管理システムの相互接続性をより高度な環境判断支援やリスク評価システムに活用することを目的としている。
2.1.5 コンピュータ科学技術レポートの環境整備(注7)
ARPAの資金のもとで、CNRI(Corporation for National Research Initiatives)では自然発生的な分散デジタル・ライブラリを連携する手法開発を行なっている。そこでは、コンピュータ科学技術レポートや関連情報の実験環境整備や、ネットワークによる検索、表示、分析技術の開発、ネットワーク環境下での電子的著作権管理技術の開発などを行なっている。この成果は、5つの大学と議会図書館の共同活動に活用されている。1995年度には、このプロジェクトは次のようなプロトタイプシステムの公開がなされている。
- 分散型デジタル・ライブラリ技術のプロトタイプは、資源蓄積管理、データ構造技術、オブジェクトベースでのマルチメディアオブジェクト利用可能なものである。
- 著作権管理システムは、電子的著作権の登録、認識、権利移転、管理などすべての領域をカバーするものである。
| (注7) |
詳細については、http://www.cnri.reston.va.us/home/cstr.htmlを参照のこと。 |
2.1.6 統合医学言語システム
(UMLS:Unified Medical Language System)(注8)
バイオ技術の進展により、バイオ関連文献、医療データベース、エキスパート知識ベースシステム、臨床事例といった異なった情報資源から検索、分析することが、研究者や実験担当者に要求されるようになってきている。そのために、異なったデジタル・ライブラリであっても関連概念で言語記述することが必要である。このような状況下で、NIHのNLM(National
Library of Medicine)では、統合医療言語システムを開発することを共同で行なっている。このプログラムは、現在では世界中に500人のユーザを持ち、概念の表現方法の標準化とさまざまな情報資源から電子的なバイオ情報を取り出すことの支援を目的としている。
現在UMLSのシソーラスは、ヴァージニア州の40以上の医療機関で電子臨床カルテの基本用語としてテストされている。最終目標は、ユーザにとってより簡単な形で、患者の記録システムや履歴データベース、症状データベース、エキスパートシステムなどと連携したものにすることである。NLMでは、UMLSを一つの情報アクセスポイントとして位置づけており、1996年度には、インターネットによるアクセスで、すべてのNLM会員に知的エージェント医療マルチデータベースの検索、利用を可能にすることが予定されている。
| (注8) |
詳細については、http://www.nlm.nih.gov/factssheets.dir/ULMS.htmlを参照のこと。 |
2.1.7 CALSライブラリ
1995年度と1996年度に、NISTではロバスト検索手法の開発と製造業で関心の高まっているCALS情報へのアクセス提供を行なうライブラリの設置を予定している。
2.1.8 研究課題及び達成度(注9)
以上のプロジェクトでのデジタル・ライブラリに関する研究課題として、1995年のIITAデジタル・ライブラリ・ワークショップ報告から、共通的な課題とその現状を以下にまとめる。
IITAのワーキンググループでは、重要な検討課題を幅広くとらえている。ほとんどのグループでは、それらの課題の優先度を検討するより先に、インフラの必要性が議論されていた。以下に示す5つのテーマのうち、(1)〜(3)まではデジタル・ライブラリの開発段階で特に重要なものであり、5つ目の経済・社会・法的問題はそれほど強調されるものではない。また、この5つの内容は互いに重なり合っている部分もある。例えば、相互操作性(1番目)の進展は厳密には、対象物をいかにうまく表現するか、うまく羅列するかといった能力(2番目)の進展に依存するからである。
| (注9) |
この評価については、Interoperability, Scaling, and Digital
Libraries Research Agenda: A Report on the May 18 19 1995, IITA Digital
Libraries Workshop August 22, 1995を中心にまとめた。 |
(1)相互操作性
- 相互操作性に関する目標の設定が困難であることは、既に議論されてきている。それらは、目的の明確化と相互操作性の範囲の設定であり、この範囲の中にある鍵となる事柄を明確にすることがそれ自身の検討すべき問題点であるから難しいのである。
-
- さらに技術的な相互操作性の検討は、幅広い操作性をカバーするプロトコルの設計に関連してくる。それらは、リポジトリ間のプロトコルであり、分散検索のためのプロトコル(さまざまなレベルにある自然発生的なデータベースを跨いだ検索を含む)や目的交換型のプロトコルである。相互操作性は、受動目的のリポジトリの中での統一性を単に用意するだけではない。デジタル・ライブラリシステムは幅広いサービスを提供し、それらのサービスはできるだけ相互操作性を持つものでなければならない。明らかにインターネットのプロトコル(WWWの基礎となっているHTTPなど)があることだけでは不十分であることが想像できよう。この点については、プロトコルやシステムといった現在の基盤を越えたところで検討がなされなければならない。さらに、プロトタイプシステムをどのように作るかや、操作性の卓越した能力とアクセスの偏在との間にあるトレードオフといった、複雑な問題も提起される。
-
- 実際の技術に根差した問題や提起された根拠に対するニーズは、相互操作性の研究に影響を与える。デジタル・ライブラリへのアクセスはほとんどのユーザにとって、アクセスそのものが最終目的ではない。むしろ支援サービスであり、多くはより高度な機能を簡単な共通ツールを使うことによって可能にすることを望んでいる。ちょうどインターネット環境下で、既存サービスの改善が新しいアプローチの大きな障害になるように、ユーザの期待と要求は、デジタル・ライブラリの相互操作性という点での基礎的な技術進展を妨げる可能性が高い。この傾向は、継続的な開発を行なっていく上での重要な要素の一つとなるため、十分なコントロールが必要である。
(2)対象とリポジトリの表現
- デジタル対象物の蓄積を密接にみようとすると、そこには分散型の検索を可能にし、離れた資源を統合するプロトコルのようなメカニズムを使うことが不可欠になってくる。対象物と対象物の集合体の表現方法は、相互操作性に大きな影響を与える。深いレベルで相互操作性を必要とするならば、対象物の検索プロトコルや検索、対象物の交換などと同様に、表現方法においてブレークスルーが必要とされる。
-
- ここでの問題は、メタデータの定義と使い方、その捕らえ方や目的からの計算、対象のコンピュータ表現の使い方、分散しているクラスター化や階層化された情報構造の自然発生的なリポジトリの統合、自動的な情報の質、ジャンルなどの評価、ランキングアルゴリズムなどがあげられる。また、知識の再現や交換といった問題や情報内容の存在論的な定義・交換なども提起される。そこでの「情報の仲介」という概念に対する議論もいくつかの報告例がある。
-
- ここでの研究は、純粋な意味でのコンピュータ技術による対象とリポジトリの表現には、強みと限界があることを理解する必要がある。さらに、人間としての図書司書が果たしてきた役割も、技術的アプローチ側からデジタル・ライブラリの中で検討する際に念頭に置いておく必要がある。
(3)蓄積の管理と組織
- 蓄積された資源の管理と組織は、これまでの従来のライブラリでの問題をそのままデジタル・ライブラリ環境に置き直したものと考えることができる。この分野は、デジタル・ライブラリがそのユーザ集団のニーズに合致したものになるためには不可欠な問題である。
-
- ネットワーク上の管理された情報資源・権利関係・支払いなどを合体させるための考え方と方法は、デジタル資源の管理での中心的課題と同じものである。分散環境下での情報の取り込みや資源蓄積間の関係をコントロールする方法は綿密な実験が必要となる。デジタル・ライブラリの内容に関する質・正確さはユーザの中心的関心事である。内容の質を決めるためには、技術と組織の間の距離の解決が必要である。また、検討の中では、ネットワーク環境下での資源管理のためには、図書司書と研究者の役割明確化も必要である。
-
- デジタル・ライブラリ環境では、テキストでない内容に対するサポート能力が必要であり、そこでは、テキストでないマルチメディア情報の取り込み、構造化、蓄積、インデックス付与、検索などが明らかに研究すべき領域である。しかし、テキストのデジタル情報も依然として重要な検討領域であり、完全な克服にはまだほど遠い。デジタル・ライブラリ環境での知識ベースは、その重要性がまだ顕在化していないが、将来重要な問題である。
-
- 長期間にわたってデジタル情報の内容を保護するためには、ハードウェアやソフトウェアの技術的世代をいくつか越えた技術・標準が重要となってくる。このことは、それほど意識されていないが、重要な検討課題である。
(4)ユーザインターフェースと人間−コンピュータ間の相互作用
- ユーザインターフェースとインタラクション(相互作用)は、それ自身範囲の広い問題であり、デジタル・ライブラリにおいてもいくつか重要な進展を見せている。
-
- 情報の提示、視覚化、情報蓄積の中での操縦や情報操作・分析ツールとの連携は、検討の中心となる領域である。
-
- ユーザの行動およびニーズに対するより洗練化したモデルの適用は、デジタル・ライブラリシステムでは、潜在的に成果の大きい領域である。デジタル・ライブラリシステムでは、ユーザのニーズ、目的、行動をより的確につかむ必要があり、それらは効果的なシステム設計に活かされることになる。最終的には、デジタル・ライブラリシステムでは、ユーザインターフェースにおいてユーザのワークステーションやネットワーク容量などのさまざまなレベルに適合できる能力がより重要になってくると考えられる。そこでは、PDA(携帯情報端末)やノマディック・コンピューティング・モデルのような新技術が、このニーズを後押ししていくものと考えられる。
(5)経済的、社会的、法的問題
- デジタル・ライブラリは、単なる技術の構造だけではない。それは、法的、社会的、経済的な内容を十分含んでおり、これらの幅広いニーズに適合する広がりをもっている。権利管理や電子情報を用いた経済モデル、それらの経済モデルを支援する支払いシステムなどが必要とされている。ユーザのプライバシーも十分注意されなければならない。そこには、蓄積された資源の管理、開発、保護、保存などの面で関連する複雑な政策的問題が存在する。既存の従来のライブラリはこれらの問題にいくらかは答を持っていると思われる。デジタル化された書類の社会的な意味は、所有権、著作権、出版権、改ざん権、翻訳権などより深い理解が必要とされる。デジタル・ライブラリが成功するためには、これらの権利関係の検討が必要なのである。
2.1.9 デジタル・ライブラリの到達目標及び課題
以上の各プロジェクトのうち、到達目標が明らかにされているものについては、次のようなものが挙げられている。
ARPA「デジタル・ライブラリ」
大学の技術レポートのサーバでの検索・処理
基本的検索・収集機構の改良
ライブラリインターフェース、知的エージェント、マルチメディア・ドキュメント・ブラウザ、非言語ブラウザのプロトコル開発
書誌情報交換のための書誌情報ネットワーク標準の開発
電子的著作権管理システム(ECMS)の設計・改良
EPA「環境データベースへの公的接続の検証」
<1995年度>
データ有効性の概要と公的公開の必要性の検討
インターネットを用いたパイロットサーバの導入
カタログ・ディレクトリ・シソーラスのソフトウェアの調査研究
NASA「デジタル・ライブラリ技術」
<1994年度>
NSF と ARPA の共同プロジェクトプログラムの導入
遠隔監視イメージデータへのアクセス支援技術の共同研究準備
<1995年度>
調査・共同研究プロジェクトの第二期開始
1994年度の成果のデモンストレーション
NASA「地球環境観察システム・デジタル・ライブラリ」
<1994年度>
DAAC(Distributed Active Archive Centers)の地球観察システム(EOS:Earth
Observing System)からのデータ成果物を導き出すオンライン「サンプラー」の導入
<1995年度>
双方向検索ツール、アクセス技術の開発
NSA「分散クロスデータベース検索」
<1994年度>
基本検索機能の拡張
<1995年度>
ナビゲーション機能とインターフェースの単純化
NSF「主要研究イニシアティブ」
共同研究機関との協力関係確立
初年度獲得したプロジェクト関連の研究集団の拡張
商用化のための技術移転環境の開発
2.1.10 今後の見通し
これらをみてくると、大きな技術的ブレークスルーとして、
分散型の巨大データベースでの双方向検索・収集技術
分散型のデータベース情報の管理技術
分散型の巨大データベースの表示技術(インターフェースを含む)
の3つが大きなものとしてまとめられる。これらの技術的課題は、そこでのサービス内容によっても左右されるものであり、どこまでサービスを追求するかによって、解決方法や手段も異なってくるといえる。
技術的ブレークスルーだけでなく、さらに、
図書館司書の果たしているエージェント機能実現技術
電子的著作権管理
なども課題として今後重みを増すものと考えられる。
デジタル・ライブラリに関しては、近い将来技術的ブレークスルーが達成できることは予想される。実際には、社会的な要因(公開可能性、課金、著作権等)が解決して初めて、全面的な普及がなされるはずである。
既に、全米図書館協会等でもデジタル・ライブラリに関する研究が進められており、米国内では、実現可能性検証段階でのマルチメディア環境下での実験が進められるものと予想される。
2.2 エレクトロニック・コマース
NISTとARPAは共同で、より効率的で経済的なビジネスデータ交換システムを作り上げることを
National Challengesとして行なっている。このビジネスデータ交換は、電子的な指示、注文、支払い、製品仕様やデザインデータの交換を行なうものである。ナショナル・パフォーマンス・レビューでは、これらデータ交換技術が連邦政府及び納税者にもたらす便益につながると指摘している。
1994年NISTはエレクトロニック・コマース技術開発機関を設立した。ここでは、ARPA、NSA、NSFなどのいくつかの機関で開発された技術を統合することを目的としている。さらに、24以上の共同研究開発要綱(CRADAs)に従う参加企業は、展示目的で器材やソフトウェアを貸し出し、電子カタログやVAN(付加価値ネットワーク)へのオンラインによるアクセスを行なっている。
これは、質問、資料請求、注文の受付などのデータ交換を、取引企業間でやりとりする付加機能をもつネットワークである。
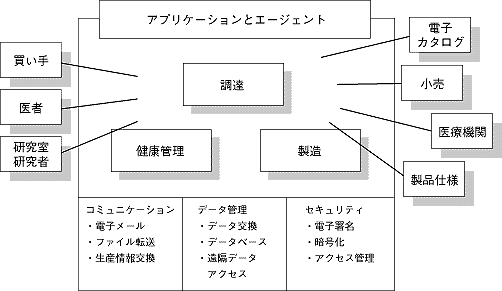
図III−3 エレクトロニック・コマースのイメージ
2.2.1 コマースネット(注10)
コマースネットは、WWWを用いた電子的な注文伝達システムのプロトタイプである。ここでは、出資は、コマースネットと企業内統合化技術とARPA's
TRP(Technology Reinvestment Program)とを合わせた形で、NIST CRADA(Cooperative
R&D Agreements)からのものである。買い手のエージェントにより、自動的に売り手の商品リストから注文を行ない、商品が割り当てられれば現時点での注文リストが値段でソートされて買い手に示される。無償で提供される技術は次のようなものである。
- スマートカードを用いたセキュリティ技術と電子メールでのデジタル署名作成技術
- 電子メールを交換する際の公開キーまたは特殊キーを用いた暗号化技術
- 初期データ交換、データの内容交換、対象者外秘のデータ交換での認証のためのセキュリティ技術
今後の想定される活動としては、Mosaicや電子メールを1つのパッケージにする高度化技術が挙げられる。
| (注10) |
詳細については、http://www.commerce.netを参照のこと。 |
2.2.2 RDA/SQLプロトタイプ(注11)
自然発生的に分散しているデータベースから情報を取り出すために、NISTはRDA(遠隔データベース標準化アクセスプロトコル)とSQL(構造化クエリー言語)を高度化している。これによって、分散データベースから情報を取り出すことが可能となる。
このインターネットベースのRDA/SQLプロトタイプは、現在3つのベンダーからアクセスできる。そこでは、分散データベースをあたかも一つのリレーションデータベースを扱うかのような形でのデモンストレーションや、エレクトロニック・コマースやその他のアプリケーションに適用できる複雑なオブジェクトから情報を得る方法などが可能となる。
| (注11) |
詳細については、http://waltz.ncsl.nist.gov/HPCC/commerce.htmlを参照のこと。 |
2.2.3 製品モデル等の情報交換標準化
1995年度と1996年度にNISTでは、製品モデルデータの情報交換標準(STEP)や他のデータ交換標準を用いた産業での共同研究を予定している。そこでは、NISTのデモ機関での戦略検討も目的とされている。
1996年度には、NISTで、インターネットベースの情報アクセス、検索、選択のためのインターフェースの提供と、それらの標準参照データ、標準参照材料の普及を予定している。
2.2.4 自動調達機能(注12)
電子メールによる購入を実現するFASTへの支援によって、ARPAでは自動調達の機能を含んだエレクトロニック・コマースでの課題に着目している。そこでのニーズは、間接費の少ない製品開発支援を国防省と産業界との間でのビジネスに対してFASTを通して実現するものである。この研究開発の問題点は、
- エレクトロニック・コマースにおける大規模な情報伝達
- 政府購入段階での生産性の向上(政府コストの低減)
- 「外国」製品コードとのインターフェース
などが挙げられる。
デジタル・ライブラリとエレクトロニック・コマースとの相乗効果が現出することにより、ARPAは1996年度に、実証的な課金機能を含んだ2つのテーマを融合した環境下での情報サービスのプロトタイプを計画している。
| (注12) |
詳細については、http://info.broker.isi.edu/1/fastを参照のこと。 |
【次へ】