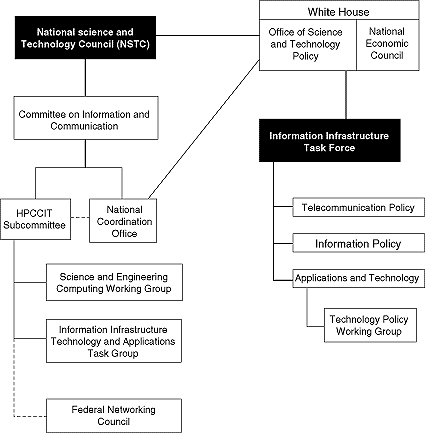
連邦政府のHPCC(High Performance Computing and Communications)プログラムは、科学技術分野における技術・アプリケーションの飛躍的発展を促進するものとして、目的付けられている。このプログラムは、GII(Global Information Infrastructure)構想を実現するための情報技術研究開発における計画・調整・投資基盤のモデルとなることを想定されている。
| (注1) | これについては、National Science and Technology Council, Committee on Information and Communicationsのレポート''High Performance Computing and Communications (Foundation for America's Information Future )''1996を基本としてまとめた。詳細については、http://www.hpcc.gov/を参照のこと。 |
HPCCは、米国の科学、数学、工学分野におけるリーダーシップを確立し、さらに、雇用の拡大や経済発展を促進する。また、情報技術の効果的な活用により、国家的セキュリティを強化し、健康で教育の行き届いた市民生活の質の向上を図るものである。この情報技術は、世界中の科学者集団だけでなく、米国の経済競争力、国家安全保障、全ての米国民の生活の質のために不可欠なものである。その情報技術の発展を加速することは、この社会における米国のリーダーシップを維持し、米国の技術優位性を高めるものである。
そのため、連邦政府はHPCCプログラムにこの役割を託し、連邦各関連部局、関連団体の参加と幅広い民間の参加を手助けするものである。
HPCCプログラムは、1991年のHigh Performance Computing Act(Public Law 102-194)から始まっている。現在では、外部環境の変化に応じて、技術開発の方向性をダイナミックに修正し続けることが求められる。
HPCCの到達目標は以下に示すとおりであるが、その中でも、長期的かつ学際的で広範な範囲を対象とするGrand Challengesと情報集約を可能にする技術の開発に特化したプログラムとしてのNational Challengesとがある。Grand Challengesは、いわば基礎研究に該当するもので、その影響範囲は科学技術に留まらず、経済全般に及ぶ。National Challengesは、国民生活の向上や国家的競争力に直接影響を及ぼすアプリケーションを主体としている。
HPCCプログラムにおいては、次の3つの到達目標が設定されている。
HPCCプログラムに関連する各関係機関は次の通りである。
HPCCプログラムは、次の5つのプログラム要素からなっている。これらの中で、Grand ChallengesはASTAに、National ChallengesはIITAに含まれている。
HPCCプログラムの評価項目は、次の7つである。
HPCCの1995年度決算、1996年度予算は次に示す規模になっている。
FY 1995 Budget (Dollars in Millions)
---------------------------------------------------------
Agency HPCS NREN ASTA IITA BRHR TOTAL
---------------------------------------------------------
ARPA 111.4 55.8 31.3 113.0 12.7 344.2
NSF 22.1 52.1 127.9 38.8 56.1 297.0
NASA 9.6 19.1 77.8 21.3 3.6 131.4
DOE 8.6 16.0 64.5 3.0 20.9 113.0
NIH 4.9 2.7 25.0 24.4 11.5 68.5
NSA 21.3 11.3 6.9 0.2 0.2 39.9
NIST 2.2 3.6 19.3 25.1
EPA 0.7 10.5 1.3 12.5*
NOAA 3.6 2.8 6.4
---------------------------------------------------------
TOTAL 177.9 163.5 351.3 240.0 106.3 1,039.0*
---------------------------------------------------------
FY 1996 Budget Request (Dollars in Millions)
---------------------------------------------------------
Agency HPCS NREN ASTA IITA BRHR TOTAL
---------------------------------------------------------
ARPA 91.0 51.7 33.9 168.4 18.1 363.1
NSF 23.5 54.7 132.6 42.7 60.1 313.6
NASA 7.6 20.9 77.0 21.8 4.0 131.3
DOE 8.7 17.0 64.3 3.0 20.5 113.5
NIH 4.1 2.3 28.1 32.6 11.7 78.8*
NSA 16.8 10.4 12.4 0.2 0.2 40.0
NIST 2.2 3.6 28.3 34.1
VA 0.2 23.4 23.6
ED 11.4 2.3 3.5 17.2
NOAA 0.7 7.4 0.5 15.4
EPA 0.7 9.3 1.0 1.0 12.0
AHCPR 0.0**
---------------------------------------------------------
TOTAL 151.7 167.6 380.0 324.2 119.1 1,124.7
---------------------------------------------------------
*Updated from the President's FY 1995 and 1996 Budget Requests.
**As a new agency to the HPCC Program,
$8.4 million AHCPR funds are not included in the total.
また、組織的には、次のような構成になっている。HPCCの活動の中心は、左中程の「HPCCIT Subcomittee」と事務局である「National Coordination Office」である。
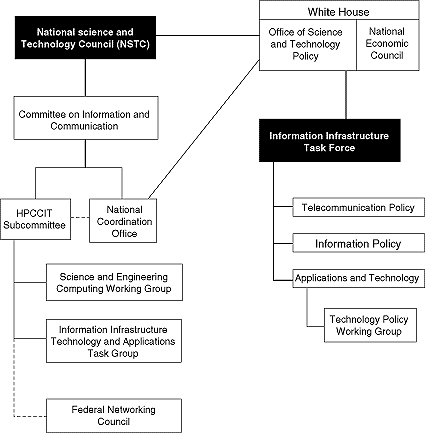
HPCCの今後の方向性、およびそこでの解決すべき課題は、1995年のHPCCの状況及び主な活動検討委員会では、次の13項目が各分野ごとに示されている。
| (注2) | これについては、National Research Council, Computer Science and Telecommunication Board; Envolving the High Performance Computing and Communications Initiatives to Support the Nation's Information Infrastructure (1995)を中心にとりまとめた。レポートの内容については、http://www.nap.edu/nap/online/hpcc/index.htmlを参照のこと。 |
このように、13の解決すべき課題をみると、明らかに現在のHPCCそのものが、各機関(省庁)の要請により肥大化しており、本来のHPCCの目的からかなり離れた分野までも背負わされている現状が浮かび上がってくる。
しかし、情報技術の発展維持のためには、HPCCの活動そのものは不可欠であることが強調されており、今後数年間にわたっては、現状レベルでのHPCCの活動は維持されるものと予想される。今後数年間でHPCCを取り巻く外部環境整備がなされれば(具体的には、他の出資機構や民間からの出資体制が整備されれば)、HPCCそのものの見直しが徐々に進められていくものと思われる。
現状の中では、HPCCのラベルさえ貼ってあれば、資金調達が簡単にできるという風潮の危険性が指摘されており、そこでの明確な活動評価、目的との整合性評価などが必要とされており、アドバイザリー委員会の設置が指摘されている。
また、HPCCのNCOにおける専従調整担当者や広報担当者が必要であることも指摘されており、NCOの機能強化と中立性が早急に必要とされているといえよう。
これまでのHPCCでの手法のうち、特に、Grand Challenges/National Challengesによる省庁間、組織間の壁を越えた柔軟かつダイナミックな研究体制づくりは成功したといえよう。しかし、そこでも研究領域の発散や商用技術への傾注など、いくつかの問題が提起されており、当初の目的通りに各プロジェクトを進行させることの難しさを示しているといえよう。そこでは、Grand Challengesの中では、明らかにHPCCの目的と分野が異なる研究範囲については、HPCCの支援範囲から除外すべきであるとの問題提起もある。そういった意味でのプロジェクト管理のあり方そのものが解決すべき課題になってきている。
ただし、このような目的に合致しているかどうかについて限定を進めていくと、本来持っている研究開発のダイナミズムが失われる可能性があり、同時に現在の我が国の支援制度のように硬直化が現れる可能性も高い。
このように13の解決すべき課題は、HPCCの活動そのものが各技術的側面での課題よりも、運営・管理体制・制度面での問題が多いことを示しており、HPCCそのもののコンセプトや方向性といった面での明確化が必要とされている。また、各関係機関間の利害調整も各課題の間に見え隠れしており、より上位レベルでのコントロール機能が必要であるといえよう。