図II−11 研究開発から技術の商業化・実用化までの流れ(ADL作成)
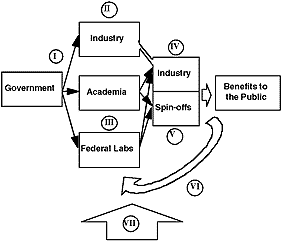
(II)産業界における委託研究
(III)大学・研究所における委託研究
(IV)大学・研究所での研究開発成果の実用化
(V)スピンオフによる技術移転
(VI)社会ニーズのフィードバック
(VII)基盤となる法体系
この節のポイント |
米国の研究開発を政策として大きなレベルで見ると、3つの基本方針が浮かび上がる。まず第一に、自由市場・競争原理の仕組みを最大限取り入れ、各自のベストな能力を自然なインセンティブの下に引き出していることである。これは規制によって行動を縛ることにより目的を達しようとするアプローチとは180度考え方が異なる。自由市場・競争原理の仕組みの下では、オープンな機会が平等に何人にも与えられ、ビジネス感覚の良い意味での緊張感が生まれる。各自は市場のインセンティブの下に、自己判断で行動を起こし、それが新たなアイデアの原動力にもなり、行動を自律することにもなっている。
第二には、研究開発成果の実用化による国民への利益を根本的な使命と明確に捉え、その成果の実用化のための仕組みを政策的に相当徹底して運営していることである。技術革新は生活水準の向上をもたらし、雇用を増やし、地域を活性化し、また米国産業の国際競争力を強める、と明確に認識されている。
第三には、実用化という国民利益の大目的のために、産業による商業化をその道とするということの明確な是認があり、最大限商業化を推進していることである。商業化については産業が行なうものというはっきりした役割分担があり、研究の成果は最大限産業へ移転する努力が行なわれている。その過程で発生する私企業の利潤は、市場メカニズムとして当然のもの、あるいは実用化の労に対する正当な報酬であると認識されている。政府出資の研究成果が私企業の利潤に加担するといった短絡的な批判を、既に超越していると言える。
以下に米国の研究開発から実用化への仕組みの全体像を示す。各部分毎に仕組みを解説していく。
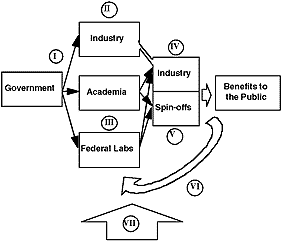 |
(I)政府による研究開発プロジェクトの委託 (II)産業界における委託研究 (III)大学・研究所における委託研究 (IV)大学・研究所での研究開発成果の実用化 (V)スピンオフによる技術移転 (VI)社会ニーズのフィードバック (VII)基盤となる法体系 |
この節のポイント |
研究開発案件を政府がプロジェクトとして研究機関に委託するに当たっては、委託先として大学、国立研究所に加えて、米国の場合産業に委託する割合が高くなっている。
ここで見て取れる基本方針としては、やはり政府資金に対するオープン市場での自由競争ということである。産官学に関係なく能力の最も高い者を採用することができるし、また世の中の最先端を間違いなく研究できる。省庁所属の研究所で行なった研究が、成果を出すころになったら既に世の中では産業界の技術より完全に遅れていた、という様な失敗も過去にはあった。また、競争原理により、次回の出資を得るために、毎回の研究で良い結果を出さなくてはという健全な緊張感も生まれている。
自由競争という以外に委託先を決定する要因としては、各省庁の使命・目的というものが大きく関わる。
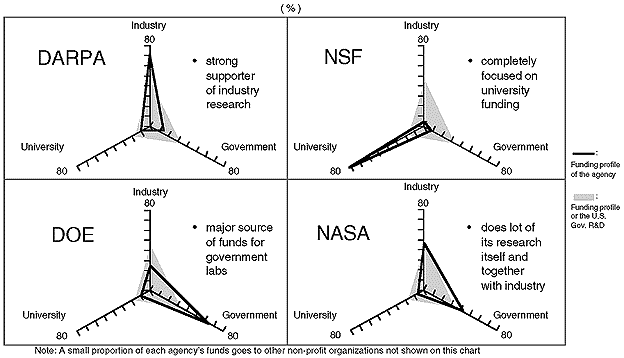
例えば科学の発展を使命とするNSFは、学問的に純粋に基礎研究に集中しやすい大学にほぼ全部出資するし、軍事技術を重要な目的とするDARPAでは、国防上軍事産業を育てておく必要から、産業への出資が最も多い。但しこれらは全体的傾向であり、同一プログラムの同一研究領域であっても、委託先には産業もあれば大学もあるといった姿になっており、自由競争・オープンな委託となっていることに変わりはない。
この節のポイント |
産業への出資は米国では盛んに行なわれていて、その重要度は出資額からしても大変大きい。
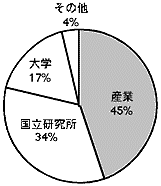
産業への研究開発の委託と一口に言っても、その形態は実に様々である。
産業への出資は、種々の省庁及び技術開発に関するプログラムから行なわれている。それぞれが違う目的を持ち、それぞれの判断で出資を行なっている。一概には省庁から直接出資の場合は政府の介入度合いの少ないProcurementやGrantの形が多く、プログラムを通じた出資の場合、より協同的なCooperative Agreementのような形が多い。以下に主な産業への出資のプログラムを見ていく。
DARPAとNASAは、政府の介入度合いの少ないアプローチを取ることが多い。その前提としているのは、受託企業が研究結果を商業化できるならば、研究開発自体も自ら管理推進できるはずだとの考え方である。しかし同時に、受託企業が政府出資プロジェクトに真剣に取り組む事を確実にするために、受託企業のコスト共同負担を要求する事が多い。
TRP(Technology Reinvestment Program)は、軍事と民生の両方に使える技術の開発を推進するプログラムであり、産業からの共同出資の方式を採用した。このプログラムが設立された経緯としては、かつて軍事技術開発を国の出資・主導でのみ行なっていた際、その技術の実用化時には民間のレベルでは既に時代遅れになっていた、という失敗の教訓から来ている。政府100%出資に比べて、産業が共同出資する技術であれば、その技術の市場性見込みはより高く、かつ研究プロジェクト後も追加の商業化投資を受けやすいはず、というのが背景となっている理論である。TRPはその後支持を失い、その考え方はJDUPO(Joint Dual-Use Project Office)に引き継がれたが、その将来は分からない。
ATP(Advanced Technology Program)は、技術の商業化性に非常に重点を置いたプログラムである。特に開発リスクが高く民間だけでは投資されづらいが、国の経済の活性化に大きく貢献する可能性のある民生技術の開発案件に対してのみ出資が行なわれる。商業化性の追及のために、ユニークな運営をしている。まず、プロジェクトの提案、研究の実行管理は企業が行なう。次に、企業が研究開発コストの半分以上を出資する。そして、プロジェクトの選択においては、学界と政府の専門家のピア・レビューにより、国の経済への貢献度の大きさが審査される。これまでATPを通じた出資額は大きく増えてきている。
SBIR(Small Business Innovation Research Program)は、ベンチャー企業の振興のために、産業に振り向けられる政府の研究開発資金の内1.25%を確保するものである。資金援助はベンチャー企業が技術・商品を開発するのに合わせ、段階毎に行なわれる。シード段階で小額の資金を受け、基礎の部分の開発に成功すると、次の商品開発段階ではより多額の資金を受けられる。商品開発も成功すると、次は市場化段階だが、それには民間資金を自ら調達しなくてはならない。逆に、市場化段階での民間資金が既に確保されている場合、商品開発段階の政府資金は自動的に受けられる。
STTR(Small Business Technology Transfer Research Program)は、SBIRと基本的に同じ目的であるが、これは協同研究予算の一定割合をベンチャー企業に振り向ける意図のもので、研究開発はベンチャー企業と大学及び国立研究所の協同で行なわれる。
産業への研究開発出資からの社会への還元は、大学や国立研究所からのそれと同様に行なわれている。
まず第一に基本的な部分としては、出資元への研究成果の報告と、その情報の公開が行なわれる。ここでも継続して出資を受けるインセンティブがあるため、不当に成果を隠す等せず、できるだけ良い結果を提出するモチベーションがある。
次に、社会還元の中で最も重要視されている面としては、研究成果を実用化することにより、国民の生活水準向上に寄与することがある。即ち、研究を行なった企業はそれを元に商品を開発し商業化することを期待されている。
ここで、なぜ政府の出資により私企業の利潤を助けるのかとの疑問もあろうが、現実はそうではない。
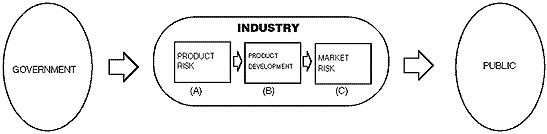
従って研究成果がそのまま私企業の利潤になることはほぼありえないことである。利潤を出すためには継続研究、商品化開発の投資をリスクを負いながら行ない、市場リスクを負いながら生産・流通をするという多大な努力が必要とされる。
とはいうものの、実際に研究成果は研究受託企業の商品開発投資によって商業化・実用化されている。その理由の一面としては、研究受託企業が最も技術を理解しその商業的価値を知っているからである。その一つの実例としては、BBN(Bolt, Beraneck and Newman)社のインターネット開発がある。言うまでもなく、現インターネット実用化の恩恵は今や計り知れないものがある。
実質としては研究を受託した企業が何らかの商業化の権利を得て、実際に商業化することは、上記のように行なわれている事が分かった。では契約的な仕組みとしてはどうなっているのかというと、その鍵となる知的所有権の所属は契約により企業であったり政府であったりする。例えば企業側が相当の研究コストを共同出資した場合等、契約交渉により、企業側に所有権が所属することはあり得る。政府出資100%の場合は、大学や非営利団体の運営する研究所には知的所有権が渡るが、営利企業には行かない法律になっている。政府はいずれの場合でも最低、無料の非排他的技術使用ライセンスを受け、他の研究への転用等問題なくできる。
知的所有権の所在に拘らず、実質的な商業化の推進は行なわれる。知的所有権を企業が持った場合でも、自己で商業化の努力をするなり他社に技術をライセンスするなりで研究成果の商業化努力がなされないと、政府はその権利を取り上げ他社を通じた商業化を試みる権利がある。また、政府が知的所有権を持った場合でも、受託企業へのライセンスや、場合によっては政府の判断で受託企業に所有権を取らせる等、まず受託企業を通じた商業化の試みから始めることとなる。
この節のポイント |
大学及び国立研究所での研究開発は勿論IT研究の根幹を成すが、その運営において、研究者の成果を高めるための、経済原理的なインセンティブが仕組みとして組み込まれているのが見て取れる。
まず、研究者がその研究成果に対して、客観的な仕組みで評価され、昇進・給与等の処遇に反映されることだ。論文として発表された研究成果は、アンケートのような形で学界・政府・あるいは産業界からのピア・レビューを受け、その研究成果の有用性、貢献度等が評価される。特に若い研究者にとってはTenure(生涯の教授の地位を保証する資格)を取ることが昇進の大きなステップで、逆にそれを取れないと大学を去ることになるという緊張感がある。
次に、研究開発のプロジェクトを受託することにインセンティブが働くことだ。多くの大学では教授らの給料は夏休み期間を除く9か月分しか支給されず、残りの3か月間分は自ら取ってくる受託研究の予算から給料を出さなくてはならない。また、競争市場でのプロジェクト受託には自らの研究能力・その領域での知識をトップクラスに保っておく必要があり、自己研鑽が自然と行なわれる。それに加え、研究開発のプロジェクトを受託し予算を取ってこられない者は、同額の給料を受け取るためには、教える授業数の負荷が増える、という経済原理に従った厳しさがある。
最後に、研究者に対する最も直接的なインセンティブは、研究成果が商業化に向けて産業にライセンスされた場合のライセンス料・ロイヤリティの約1/3が研究者個人の収入になることだ。1980年のBayh-Dole Actにより、政府出資プロジェクトの成果について大学・国立研究所が知的所有権を持てることになったが、それとともに研究者個人への金銭の分配も法的に定められた。
この節のポイント |
研究開発が行なわれた成果は、次に商業化・実用化されることが大変に重要視されているが、そのための産業への技術移転には、法的な知的所有権の設定を初めとするインセンティブ・市場原理が導入されている。
まず初めに、大学・研究所は、自らの役割をはっきりと産業と区別している。
Universities/Federal Laboratories |
Industry |
大学・研究所が行なう研究は、中長期的視点に立った、物事の本質的な究明であり、短期的な技術の実用化や産業の問題解決は行なわない。後者は課税対象でもあり、非営利の大学・研究所では行なえない。であるからして、後者の段階にはいる前に、技術は産業に移転されるべきという考え方ははっきり認識されている。
技術移転については、80年〜87年の法整備を受けて、大学・研究所でもその後組織的な取り組みをしてきた。Stanford、MITを筆頭にその成功と大学側へのメリットが認識され、ここ数年から現在にかけて、他の多くの大学・研究所が重要事項として積極的に取り組んできている。
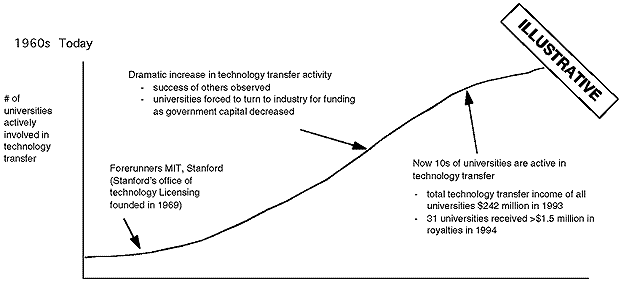
技術移転の仕組みとしては、まず大学・研究所、及び研究者個人に金銭的インセンティブが導入されたことである。80年のBayh-Dole Actによって政府出資研究成果の知的所有権は非営利の大学・研究所に属することとなり、大学・研究所ではそれをマーケティング、ライセンスすることで、相当の収入が入ってくることとなった。ライセンス料、ロイヤリティ収入の内の相当部分(通常1/3程度)は法に定めるように研究者個人の収入となり、研究者個人にも大きな成功報酬というインセンティブが生まれた。
これに基づき、大学・研究所では、技術移転事務所や技術ライセンス事務所を作り、積極的活動を行なうようになってきた。
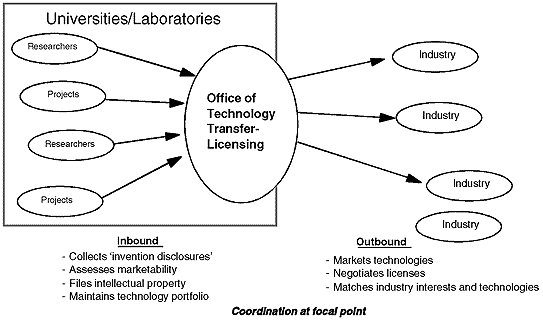
同事務所では、研究者に代わって特許取得の事務を行なったり、大学・研究所の窓口となって、特許化された技術のマーケティング、及びライセンスの交渉・事務を産業相手に行なっている。技術案件が研究者から出されると、その商業化の可能性を事務所で判断し、特許化する価値のあるものはし、関連業種等のターゲット企業に直接売り込む努力まで行なう。
ライセンス供与についても実用化を最大の目的とした上で、市場に合わせた柔軟な対応をしている。ライセンスは非独占的に多くの企業に出していくという考え方も一面では正しいが、場合によってはライセンスの独占供与をすることがより商業化につながると考えられる場合、独占供与も行なう。特に商業化開発のリスクの高い場合、独占供与という保護によって商業化後の投資回収の確率を高め、リスクを減らす措置を大学・研究所の判断で行なう。しかし同時に、ライセンス保持者が商業化の努力を十分にしない場合、大学・研究所はライセンスを没収し、他者を通じて商業化する権利を持つのが慣わしとなっている。
産業への研究成果の移転・商業化が大学・研究所にとっても利益があることが分かってくると、今度はその移転先の産業を大学・研究所での研究開発活動に近付けること、即ち産学連携の努力がなされてきた。産業側にとっても技術移転は利益のあることであり、MITやStanford等の先行校に加えて、ここ数年でその動きが非常に活発化してきている。
産学連携の意義としては、大学・研究所側の利益としては、研究資金源が得られることが最も直接的なものである。それに加えて、世の中の動き・現実的な課題を常に知る事ができることなども挙げられる。産業側にとっては、研究成果に早くアクセスできたり、他社に先行してライセンスを交渉する権利などが通常ある。それらに加えて、研究者とのコンタクトができること、そして最も大きな技術移転の方法であるとも言われる優秀な学生を採用できることである。これら両者の利益を実現する中で、大きく見ると技術の移転・商業化を推進するという社会的な目的も果たしていることになる。
産学連携の形態としては、色々なレベルがある。
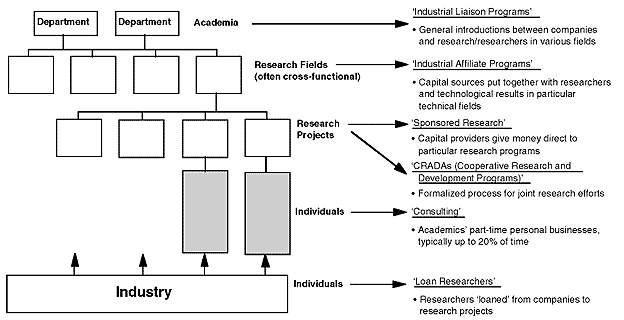
まず大学を代表する窓口として、色々な分野の技術・研究者を紹介する年会員制のプログラム(Industrial Liaison Program)、特定の研究領域において研究資金供出とともに研究者や研究結果への技術的レベルでのアクセスを可能にするプログラム(Industrial Affiliate Program)、そしてある特定の研究者の研究に出資する直接研究支援(Sponcered Research)がある。尚、昔からの寄付・奨学金等はここでは含めていない。それ以外には教授が個人のビジネスとして行なうコンサルティング(米国では兼業可能、むしろ奨励されている)、企業からの研究員の受入等の交流もある。
いずれの形をとっても、大学・研究所で行なう研究は、あくまで研究者主導であり、成果の知的所有権は大学・研究所に帰属する契約にしているのが通例である。しかしながら、ライセンスの先交渉権、企業側でのライセンス検討のための成果発表一定期間留保や、ライセンスのオプション契約等、企業側にも便宜を図っている。
この産学連携も、投資と見返りが意味を成す健全なビジネス的関係の中で、切磋琢磨の緊張感を持ちつつ成り立っていると言える。
この節のポイント |
スピンオフとは、大学や研究所の教授等研究員が大学・研究所を離れ自分の研究成果を自ら商業化するためにベンチャー企業を起こすことである。これは大学・研究所からの技術の商業化として、ITの世界では特に重要な一つのメカニズムとなっている。自由市場における究極とも言えるハイリスク・ハイリターンのベンチャーに、研究者は一獲千金を狙って大胆に挑んでいる。
大学・研究所からの技術の商業化としてスピンオフを見ると、それは既存の産業に技術をライセンスするのとの選択肢の一つとなっている。研究成果が出ても、大学のライセンス事務所では例えば特許化の価値がないと判断されるとか、商業化性が低いと判断される技術の数は多い。その中で、研究者個人としてはその商業化性を信じ、自ら技術のライセンスを大学から受けて企業を起こすのがスピンオフの典型的形態である。
スピンオフは、一般のベンチャー企業と同様、ハイリスク・ハイリターンである。その成功したときの収入から来る金銭的インセンティブは強力であるが、同時に成功の確率も低い。社会的に見れば、技術の商業化の成功に向かって、強力なモチベーションが働く仕組みとなっている。
大学としては、その技術移転における重要性を認識し、最近はスピンオフを組織的に支援する体制を取りつつあるところが多い。例えば教授に対しては2年間の休職を認め、その間に会社を立ち上げ、復職時にも問題がないようにしている。また、大学での研究成果の知的所有権を大学が持つのは同様だが、それをライセンスするときに対価を一部株での支払を認めることも行なっている。また、更に積極的な所では、スピンオフのベンチャー企業の育成を大学内で行なうため、大学でベンチャーキャピタル的資金を持つ構想もある。最近ではCarnegie Mellonの技術移転事務所がベンチャーキャピタルの紹介に始まるベンチャー立ち上げの支援を行なう中で、Lycosを商業化し、約150億円の会社価値にするまでの成功を挙げた。
スピンオフ先行組のMIT、Stanfordでは、大学として特別の支援はしてきていないが、ベンチャーキャピタルを初めとして周辺地域にIT産業に関する資金・人材の流動する市場ができている。
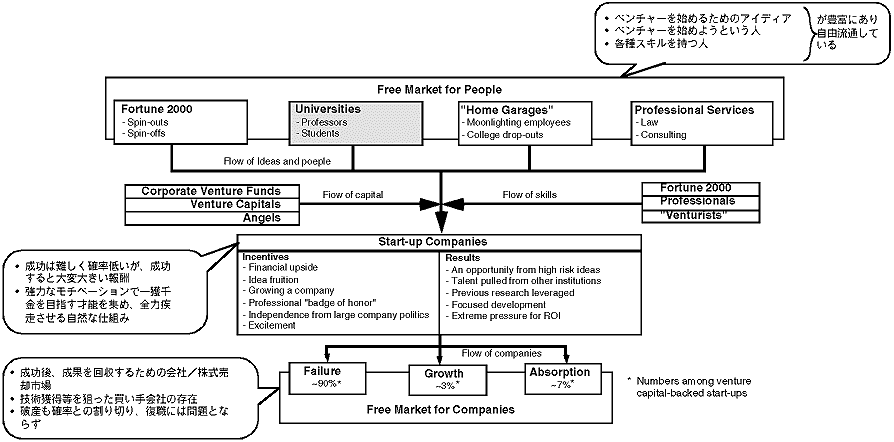
まず起業家精神が誰もに認識されほぼ文化となっていることから、人材やベンチャーのアイデアは常に豊富に流通しており、その自由市場を形成している。それを動かす動機になっているのは、ハイリスクで成功確率は低いものの、うまくいった時のリターンが非常に大きいベンチャー企業の本質である。これが優秀な人材を引き寄せ、全力疾走で働かせている。それに加え、ベンチャー企業の後始末の市場もできており、会社をそのまま成長・株式公開させるだけでなく、売却の市場もある。大手のIT会社は新技術の獲得等を目的に、積極的にベンチャー企業の買収を行なっている。また、破産したからといって、復職には問題はない風土になっている。
正に自由市場の中でベンチャー企業を育成し、また淘汰を行なう、インフラとも言える仕組みが機能している。
大学・研究所では、自ら選択したテーマに関する研究成果の産業への移転を一方的に行なうだけでなく、産業の声を世の中のニーズを反映するものとして聞くことを行なっている。大学での研究は学問的興味において、産業等と独立した中で自由に行なうことが原則であり、それは守られているのだが、それにしても研究テーマが世の中の本質的課題により対応するように影響を受けたりしている。
産学連携におけるコミュニケーションの場の設定は、それだけでも相当、産業からのフィードバックを受ける機会を作っている。また、政府資金源が漸減する中で、産業から出資を受ける関係上、自然と産業に耳を傾けるインセンティブが働いている。
それを加速しているのは、ATP等に見られる政府出資プログラムが、より産業からの共同出資を条件とする方向に動いてきていることである。これは産学連携、商業化重視の方向性を、大学・研究所に対しても強力に推し進める原動力となってきている。
この節のポイント |
米国では政策レベルで技術を産業に移転して商業化・実用化を行なうという基本方針があるが、それを実現する基盤となる法律を数々作ってきている。
最も基礎的なレベルでは、66年の情報公開法により、政府出資の研究成果は須らく公表するということになった。その後80年のSteven-Wydler法とBayh-Dole法により、技術は市場メカニズムで産業に移転するもの、という今日の技術移転の基礎の仕組みが作られた。特にBayh-Dole法は大学・研究所に政府出資の研究成果の知的所有権を与えたので、実質的に技術の市場を作り出すこととなり、その後大学はこぞって技術移転のビジネスに乗り出した。研究者及び大学・研究所にはライセンス収入からの大きな金銭的インセンティブが働くこととなり、その後大学・研究所では技術移転の組織的成功への大変大きな努力がなされてきている。
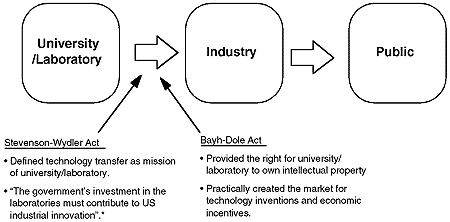
このように数々の法令が出されているが、いずれもその目的は何か行動を規制するのではなく、自由市場メカニズムをより良く働かせて研究開発活動及び商業化を推進するための仕組みを提供するためのものである。法令はあくまで、基礎を提供するか一部方向性を示すサポートの役割であり、実際の多くの部分は、自由市場での自己判断での運営の部分が、全体の仕組みをうまく動かしている原動力であると言える。
以上米国の研究開発政策の方針と研究開発の仕組みを見てきて、以下のようなことが学べる。