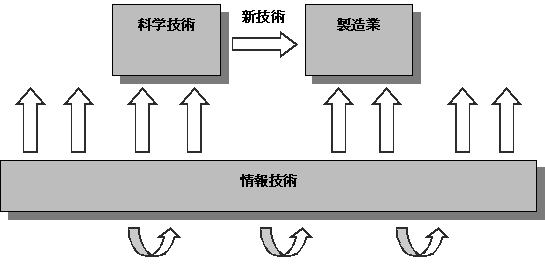
8.韓国
韓国の情報化陣tノ関する主管官庁は1992年まで通信部と商工部に分かれていたが、同年統合され、情報通信部(MIC; Ministry of Information and Communication)が新設された。金大中政権発足後は、情報産業がIMF体制克服のための産業効率化における「戦略産業」であると位置づけ、情報化政策を強化推進している。
8
.1 韓国情報基盤(KII)1995年にスタートした韓国情報基盤イニシアティブ(KII; Korea Information Infrastructure Initiative)に基づき、翌年情報化促進基本計画が策定され、さらに1997年には情報化促進アクションプランが明らかになった。情報化基本計画は、3つのフェーズから構成されており、それぞれのフェーズの目標が規定されている。2000年までの第1フェーズでは、優先度の高い10のタスクとして下記が掲げられている。
小さいが、電子化され効率的な政府を実現する
情報社会で有用な人材を育てるための教育情報基盤を構築する
国家の知識ベースを拡充するために学術研究データにアクセスできる環境を作る
産業全体にわたり情報化を促進し、企業競争力を高める
情報化により社会インフラの利用率を高める
地域開発に向けて地方の情報化を支援する
情報技術の利用により医療サービスを向上させる
災害対策のための安全管理データシステムを構築する
国防・外交情報システムのセキュリティを高める
韓国政府は、情報化の基盤である
KII構築を重要政策として推進している。計画では、韓国政府情報基盤(KII-G)と韓国公用情報基盤(KII-P)を2010年までに完成させる予定である。まず、KII-GをATMベースの光ケーブルネットワークにより2002年までに完成させ、その後KII-Pプロジェクトを推進する計画である。1988年の白書「21世紀の情報社会の構築」によれば、現時点で、ネットワークは、ソウル、プサン等を含む80の地域に展開されている。主要都市では電話局と配信先の間に光ケーブルが敷設され、光ファイバケーブルは1,018の大規模ビルに敷設された。N-ISDNは103の地域が利用可能となり、配信先は合計66,300箇所となった。CATVネットワークの配信先は合計7.44百万箇所となった。
8
.2 情報社会に向けての韓国のビジョン1999年3月現在、情報通信部はインターネットに発表している「情報社会に向けての韓国のビジョン」の中で、次のような方向を示している。
(
1) 生産性の向上
◆政府のリエンジニアリング
PCを与えることにより、ペーパーレス政府が実現できる。また、1998年には政府、自治体ごとにCIOを任命した。政府調達にはEDIを導入する。市民サービスはインターネットを通じて行えるようにする。政府機関を高速ネットワークで結び、職員に
◆企業リストラの支援
ERPとコンサルティング方法論を開発する。韓国標準の税務、会計モジュール等の
◆電子商取引の促進
CALSで、EC市場化を図っている。いくつかのプロジェクトでは、消費者向けのECが開発されている。ECのための技術開発と標準化作業が行われている。政府調達、国防と建設分野の
◆QOL
(クオリティオブライフ)のための情報化教育のための情報環境、ヘルスケア・福祉のための情報化、国防・環境管理のための情報化、文化と情報化、地域コミュニティの情報化を進めていく。
(
1) よりよい情報化環境の構築
◆KIS
(韓国情報スーパーハイウェイ)の構築(KII)知識ベース経済において、経済活動の中心はコミュニケーションである。そのために必要な高速情報ネットワークを早期に構築する。
◆テストベッドネットワークと地域パイロットプロジェクト
中小企業が先端技術の研究開発に利用できるような共同研究開発センターを設置した。
◆APII
1997年の韓日テストベットプロジェクトに基づき、韓国−シンガポール、韓国−中国テストベットプロジェクトを実施する。ソウルにAPII共同センターを設置した。
◆関連法規制のオーバーホール
1995年から1997年にかけ、63の法改正を行った。引き続き、関連法の見直しを行っていく。
◆通信サービス利用の環境改善
通信サービス利用の環境改善として、PC普及率の向上促進、情報技術リテラシーの改善、優良なコンテンツの開発、情報化キャンペーンの実施を図っていく。
◆効率的なセキュリティ指標
インターネットとオンラインサービスの拡大に伴い、効率的なセキュリティ指標の快活を急ぐ必要がある。
◆Y2K
問題の解決2000年問題の解決状況を評価する。また、中小企業向けに2000年問題対応のための融資を行う。定期的に
9
. 各国の情報化ビジョン/政策の比較と特徴
以上の各国の情報化ビジョン/政策の調査結果に基づき、各国の状況を比較し、全般的な傾向・特徴を整理する。
9
.1 情報化ビジョン・政策の位置づけと推進方法情報化ビジョン・政策の位置づけと推進方法に関して、以下のような特徴を指摘することができる。
(
1) 情報化が21世紀の国の戦略課題であることの認識今回調査した国は、いずれも情報技術が社会、経済に多大な影響を与え、経済活動を効率化し、国民生活を豊かにする上で情報化が極めて重要な要素であることを指摘している。また、情報通信産業を、それを実現するため、経済発展のための戦略産業として位置づけ、国際競争力の強化・育成を図ろうとしている。
また、このような認識の背景として、工業経済から情報経済へのシフトが進んでいること、その中で情報や知識の付加価値が高まることを理解し、産業界等関係者に対する啓発を進めている。
(
2) トップレベル組織による強力なリーダーシップ情報化に係るイニシアティブ、プログラムを、国の元首直轄の組織として統括し、強力なリーダーシップをもって実施している場合が多い。
アメリカのクリントン=ゴアや、マレーシアのマハティールのように、国家元首自身がリーダーシップを発揮し、情報化プログラムを推進している場合もある。また、それ以外の国においても、省庁の壁を超えた機能横断委員会を設置し、国家レベルの重要課題として情報化プログラムを推進している。
また、省庁レベルでも、情報と通信・放送の技術的・サービス的融合を踏まえ、ここ数年間で情報産業と電気通信産業の主管官庁を統合した国が多い。
(
3) 政策立案過程でのインターネットによる対話の利用情報社会では政策立案過程自体の変革も求められる。各国の政策立案過程において、インターネットが有効に使われていた。インターネットで政策案を開示し、それに対するフィードバックコメントを受け付けているケースが多い。例えば、インドにおいては、インターネットにより政策課題に関して広く意見を集め、計画策定していくという方式を採用していた。
(
4) 国の役割と民間部門との連携国と民間部門との連携も重要な側面である。今回調査した国の情報化ビジョン・政策では、国の役割を次のように設定していた。
|
情報社会のための高速・大容量通信ネットワークの整備 情報社会に必要となる法体系(知的財産権、プライバシー保護、決済等)の整備 電子商取引等新たなアプリケーション構築に必要な技術開発の支援(助成等) イノベーションと公正競争、そしてリスク回避のための規格・技術標準の調整 電子商取引等新たなアプリケーション立ち上げのためのパイロットプロジェクトの推進 情報通信産業を育成するためのベンチャー企業の支援(税制支援、助成等) |
これらに対して、民間企業は、パイロットプロジェクトへの参画、研究開発の補助、ベンチャー起業によって貢献することになる。しかし、商品化や起業化に関して国がどこまでコミットできるかについては議論が分かれる。
(
5) 他国、他地域との連携情報社会においては、いろいろな面でグローバル化が進展する。したがって、各国の情報化ビジョン、政策も地球規模の視野を有している。
規格・技術標準や取引ルールに関しては、国際標準化機構(
ISO)、世界貿易機関(WTO)、世界知的所有権機関(WIPO)といった国際機関との調整が必要であり、また業界におけるワールドクラスのリーダー企業を無視することはできない。また、自国の産業競争力を高めるためには、国際的な分業とアライアンスという観点から自国産業のポジショニングをする必要がある。さらに、技術、資金の国際調達が必要であれば、それに適した優遇税制等の環境づくりが必要である。
今回の調査対象国では、他国、他地域との連携範囲は異なるが、いずれも地球規模での情報社会の進展を見通している。
9
.2 情報化ビジョン/政策の内容情報化ビジョン・政策の内容に関しては、以下のような特徴を指摘することができる。
(
1) 持続的成長と中長期的課題の重視前節で指摘したように、国の役割としては、基盤・環境整備が重視されていた。また、情報社会の進展と同時に、将来の大きな課題として指摘されている「環境」「健康・医療」「高齢者福祉」といった問題解決に貢献する視点も掲げられている場合が多い。
(
2) 通信インフラの整備と情報通信・放送産業の改革情報社会においては、情報・知識を伝達する通信インフラが極めて重要である。マルチメディア技術、ディジタル技術、インターネットの発展をいち早く取り入れ、情報社会を先導していくために、各国では通信インフラの整備を最優先課題として取り組んでいる。
また、それを推進するための事業主体を整備し、国際競争力を高めるため、情報通信産業および放送産業の規制緩和を推進している。
(
3) 産業の情報化 〜 電子商取引の推進情報社会の実現の中でも、産業の国際競争力を左右する産業の情報化が大きなテーマとなっている。具体的には、電子商取引の推進であり、各国では、電子商取引の基本枠組みやアクションプランが策定されている。
アクションプランの構成としては、電子商取引を支える取引ルールの標準化や法体系の整備、それを実現するための技術開発(認証、暗号等)、普及加速のためのパイロットプロジェクトの推進等が挙げられる。
(
4) 行政の電子化行政の電子化も調査した国すべてで実施されていた項目である。行政サービスのネットワーク提供、行政事務の効率化を狙ったものが多い。
行政の電子化は、新たな情報技術に関して初期需要を作るという役割もあり、情報産業育成の観点からも重要視している国が多い。
(
5) 科学技術研究の支援・環境整備今回調査した国の中では、アメリカとEUに関しては、政策の中でも科学技術研究の支援や環境整備も重要な位置づけになっていた。他の国では、産業、社会に対する応用研究や学校教育環境整備に関する取り組みはなされているが、科学技術研究自体への支援は比較的軽い。
(
6) 先進的アプリケーションの開発・育成 〜 技術とビジネスモデルの協創各国の情報化の展開において、先進的なアプリケーションの開発・育成を重視している。インターネット上での検索エンジン、情報提供サービス、サイバーショップ、さらにはネット・オークションといったビジネスモデルは、
http、WWWといった新たなインターネット技術によって創造されたともいえる。このように、潜在需要が顕在化するプロセスは新たな技術を媒介にした創発的プロセスである。各国では、このような観点からマルチメディア、インターネットといった新技術の用途開発を指向している。
(
7) 関連法規の整備電子商取引の項でも指摘したが、情報社会において必要となる法規制が必要となる。コンテンツや技術に関する知的財産権、個人情報等の扱いに係るプライバシー保護の問題、電子商取引に係る認証、決済等の問題である。各国ではこれらの点に関する法体系の見直しと整備が進められている。
10
. わが国の情報化ビジョン策定に関する考察10
.1 概要前章まで、情報技術先進国ないし情報先進国を目指す各国の情報化ビジョンを調査・分析してきた。それぞれの国が情報技術を産業・社会の重要基盤と認識して、国家の高いレベルにおいて情報化ビジョンを打ち出し、それぞれの事情に応じた基盤の整備ないし研究開発を展開しつつある。米国では情報スーパーハイウェイ構想で情報技術基盤を掲げ、
HPCC 計画等により科学技術分野を支援し、民間も戦略的な情報技術投資を積極的に行なっており、現在の好調な経済状態を支えている。さらに、今年に入って PITAC報告やビジョンでは基礎的研究開発を重視して中長期的な発展を保証しようとしている。国内市場の規模が小さく、独自の情報技術開発力の小さいシンガポールやマレーシアなどでは、国際標準の先進的な情報技術基盤を整備することによって、地域のハブとしての地位の強化や先進的企業の誘致を図っている。オーストラリア、インド、韓国でも情報産業の強化、情報基盤の整備を活発に進めている。わが国は国土が狭く、天然資源に乏しいが、教育水準が高く、勤勉な国民性を背景に、国際的競争力を持つ基幹製造業によって経済的発展が築かれてきた。今後もわが国の繁栄にとって、高度な技術に支えられた製造業の強さが最も重要な前提となろう。そこで、わが国における情報化ビジョンは、21世紀に向けた製造業の高度化を狙いとするのが適当である。製造業の高度化を直接に担うのは各企業だが、情報社会基盤の整備や基礎的な研究開発は国が推進する必要があり、情報化ビジョンはそれらの重点的課題と考え方を示すものとする。
情報社会基盤・環境の整備としては、ネットワーク・通信インフラ整備・強化の支援、ネットワーク新技術実験の支援、法律・規制などの制度の情報化社会に向けた適合化から人材育成などがある。
(基礎的な研究開発は、長期的でリスクを伴うため、国が推進すべきであり、特に、(1) デバイス基礎技術からヒューマンインタフェースに至る情報技術の基礎研究、(2) 科学技術研究開発の方法を革新しつつある計算科学(計算機による仮想実験)やインフォマティクス(大量の情報整理・解析技術) が、情報産業を含む製造業の強化のために重要な研究開発推進領域と考えられる。その他、ソフトウェア産業の強化、より効果の高い国の推進・支援する研究開発のあり方の実現、等、わが国独自に取り組むべき個別的な課題もある。
10
.2 情報社会基盤・環境の整備の考え方 狭い意味の情報社会基盤・環境の整備は、ネットワーク・通信インフラ整備・強化の支援、ネットワーク新技術実験の支援、法律・規制などの制度面など、目に見える情報通信インフラと制度的インフラである。これらは短期的に取り組むべき課題でる。 広い意味の情報社会基盤・環境の整備は、人材や競争的環境など、無形のものであり、中長期的な取り組みを必要とする。情報技術を担う人材の育成は重要課題であり、先端技術開発、実用技術開発、技術要素を組み合わせて実際の問題に適用するシステム技術といったスペクトルを厚くカバーする必要がある。 わが国の製造業は、国内市場の厳しい競争、利用者の厳しい注文が鍛え、世界をリードする品質に高められたと言われている。情報産業においては、導入側の利用技術や比較評価力が十分でない等により、必ずしも競争的環境にあると言えず、競争的環境実現に向けた方策を考えるべきである。 また、情報技術を現実の問題に適用する担い手であるソフトウェアビジネスの強化は重要な課題である。依然として、受託開発の割合が高く、またその効率が必ずしも高くない問題を徐々に改善して行く方策が検討されるべきである。
10
.3 情報技術の研究開発の考え方(
1) 基礎的研究開発テーマの推進 実用化・製品化から遠く、研究開発コストが大きく、民間企業が取り組むにはリスクの大きいテーマを中心に国は取り組むべきである。中長期的に育つ可能性のある技術の種を蒔くということであり、特に、重要な(潜在的)ニーズの発掘が重要である。そして、実用化・製品化の目処のついた研究成果は公開し、民間が自由に実用化・製品化し、公共の利益に結び付くという形で研究開発投が回収されることを目指すことが基本である。 なお、ネットワークのように基本インフラとなる技術については、独自技術開発の能力があっても、国際標準とならなければ却って孤立化を招くため、国際的な協調を図ることが適当であろう。
(
2) 実用化・製品化に近いテーマの研究開発の民間主導 実用化・製品化に近いテーマは周辺技術を開発中であることが多く、成果における知的財産権の切り分けが問題となるなど不都合がある。むしろ、資金貸し付けや優遇税制などの環境面のバックアップが適当と考える。ただし、過剰な補助金等によって、不要ないし見込みの低い開発が促されることがあり得る。そして、成果である先進的な製品・サービス等を積極的に調達し、実地に用いて育てるべきである。(これは国が基礎研究を支援した技術に限らない。)
(
3) 実験的・研究的ソフトウェアの実用化大学等で基礎的研究がなされた技術の芽を育てて行く必要がある。有望な計算手法やソフトウェアの芽を、一般の利用に耐えるソフトウェアとして体現し、
(無償)公開し、ユーザコミュニティが育つまで必要なメンテナンスを行なうことが可能となる仕組みを実現すべきである。
10
.4 研究開発課題について研究開発の課題設定に当たっては、現在の変化に着目するのみならず、
(一定の幅を持った)将来の情報社会像を想定し、そこにおいて重要となる技術要素の研究開発、社会経済的な課題の予期・対策検討といったトップダウン的なアプローチを併用するのが適当と考えられる。また、電子商取引や放送通信など国際的標準の形成が重要な領域では、各領域でのわが国の相対的な力を考慮した国際競合・協調を含む戦略の検討も必要であろう。また、研究テーマの実施に当たって、最終的にインパクトのある成果活用に結び付く研究開発のあり方なども課題である。基本的には、わが国が研究開発力を持っており発展の続いている分野における中長期的目標実現の支援、ネットワークが遍在化し、小型の情報通信装置が社会・経済活動や日常生活にますます浸透し、集められた大量のデータの解析による発見が価値を生むような将来像において、キーとなるであろう技術の先行研究などが重要と考えられる。また、科学技術分野では理論、実験と並んで計算科学
(シミュレーション計算やインフォマティクス)が研究手段として重要性を増しており、新材料・新製品の設計開発の方法論を変えて行くと言われている。その分野の強化も重要課題である。
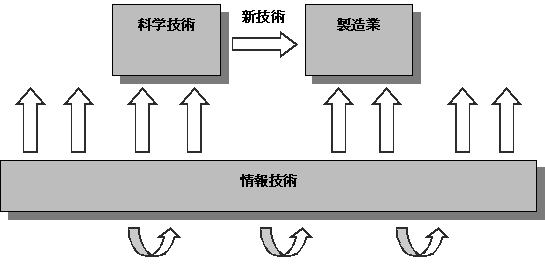
情報化ビジョンの考え方: 製造業を強化する情報技術